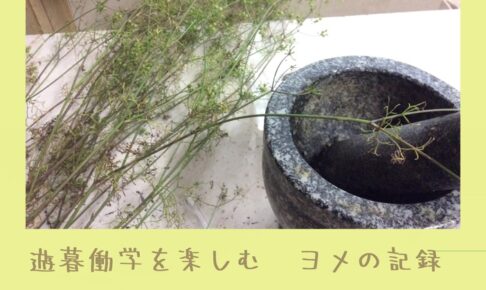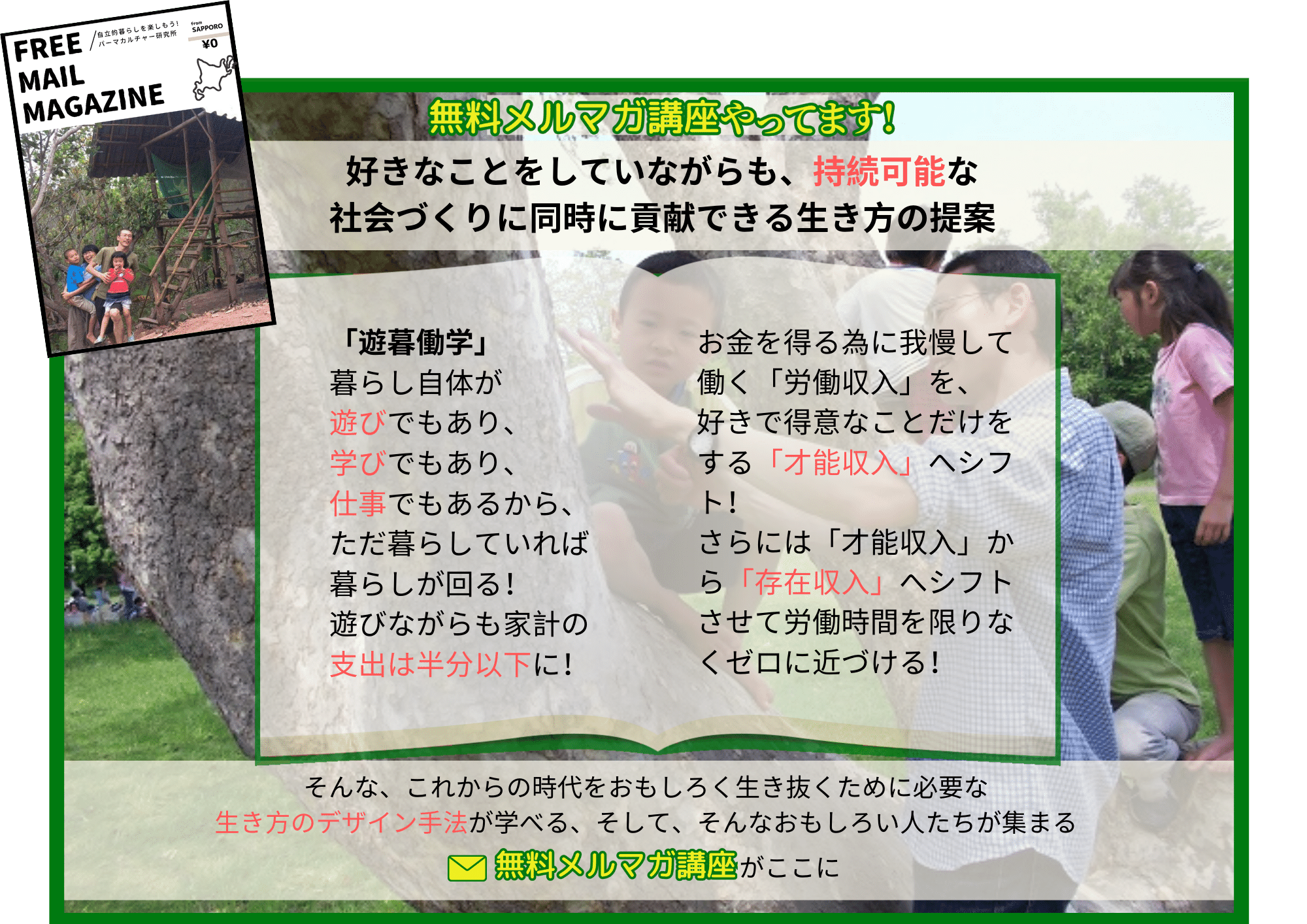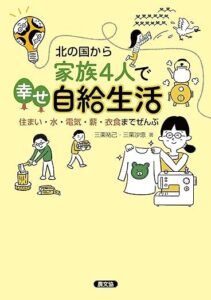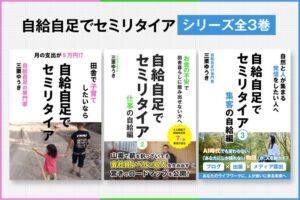1.収穫の時期
8月下旬、収穫真っ盛りの時期のお話です。
とは言っても、5月の日照りから始まり、気温の高さに負けたのか、
今年は収量の少ない年。
中でも気になったのは豆科のお野菜たち。
大豆もささげも発芽できる種も少なめ、花がつくのもゆっくりでした。
例年、札幌では8月にはこれでもかというくらい次々に、ささげが取れますが、今年はツルばかりが成長して、このまま花が咲かずに終わるのかな?と思った矢先。。
8月の終わり、急に花がついたと思ったら、実がなりはじめ、びっくりするとともに嬉しい気持ちでいっぱい(^_^)w

植物の気分が変わったかのように急に花が咲き、実り始める。。。
そんなことがあるんですね。
植物もまた、不思議です。
近頃の気温をどう受け入れて、こんな動きになったのでしょう?
早速収穫してきて、新じゃがと煮たり、炒めてみたり。。
とれたての甘さを楽しんでいます。
流通にかかる時間でお野菜の糖度ってだいぶ変わるので、
新鮮な味を楽しめるのが家庭菜園の醍醐味です。
それから今年の記録としてもう一つ。
暑さの影響でしょうか。
きゅうりもナスもトマトも皮が硬いものが目立ちました。
植物も身を守るために必死なんですね。
今年も観察し、感じて学んで畑のこと。
自然とともに暮らしがあるって面白いです。
2.家庭菜園で作る玉ねぎ
去年の雑草で作った草堆肥を入れた一列と、牛糞を入れた一列を作り、
二列に玉ねぎを植えてみました。途中での肥料の追加はナシです。
雪国なので早春に植えて、7月末には収穫になります。
雑草だけ抜きつつ、時々お水をあげながらお世話をしましたよ。
こんなに大きくなってくれました。

大きさは大人女性の拳ほど。
思ったより大きく育ってくれました(^-^)v
そして二列の対比実験はほぼ同じ大きさでの収穫となりました。

収穫をしたら、根っこと葉の部分をカットして乾かしてコンテナへ。
来年は一年分育てられたらいいなあ。
3.家庭菜園で作るニンニク
玉ねぎやそら豆は越冬できませんが、ニンニクは雪の下でも越冬してくれます。
(関東以南あたりは秋に植えて春にほりますよね。)
毎年9月に種を植えるニンニクの収穫時期は7月の終わり。
2年前から、生ゴミコンポストの跡地をニンニク植え場にしています。
ニンニクは結構栄養を必要とするのですが、コンポストの跡地では追肥をやらずとも結構大きくなってくれるので、いつの間にやら、毎年コンポストを追いかけるようにニンニクを植えています😊。。
植える場所にも迷わないので、今年もタネはコンポスト跡地に植えるべく、準備を始めています。

掘った後は乾燥と魔除けも兼ねて玄関先へ、笑。

4.土に触れながら思うこと
土に触れ観察をする暮らしの中で、
Yukiから聞いた畑の師匠の言葉を思い出します。
“どんな年でも、すべてが「いい」ということも、「悪い」ということもない。”
野菜を育てる上で、あるいは収穫する上で、
「すべての野菜が問題なく収穫できる=いい」ということも
「すべての野菜がダメになっている=悪い」ということもない。
毎年、出来がいいものもあれば、悪いものもあり、
そうしてバランスが取れているんだなって思い出します。
今年も、自然が与えてくれたものがあり、それを大事に頂きながら夏が過ぎていきます。
土に触れることで、人が思うように動かすことができない自然の深さを思い知り、
目の前を受け入れるしなやかさをこうして少しずつ身につけさせてもらっています。
今年も恵みに感謝です。
暮らしが学び、暮らしが遊び。そして暮らし自体が仕事。そんな、ただ暮らしてるだけでという究極のライフスタイル、「遊暮働学(ゆうぼどうがく)」。このライフスタイルの作り方を、無料のメルマガで解説しています。
読んで見たい方は、下のフォームからご登録ください。メールアドレスだけでも登録できますよ。