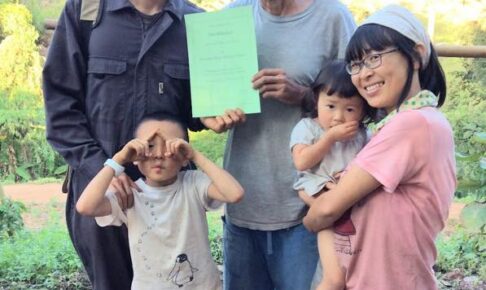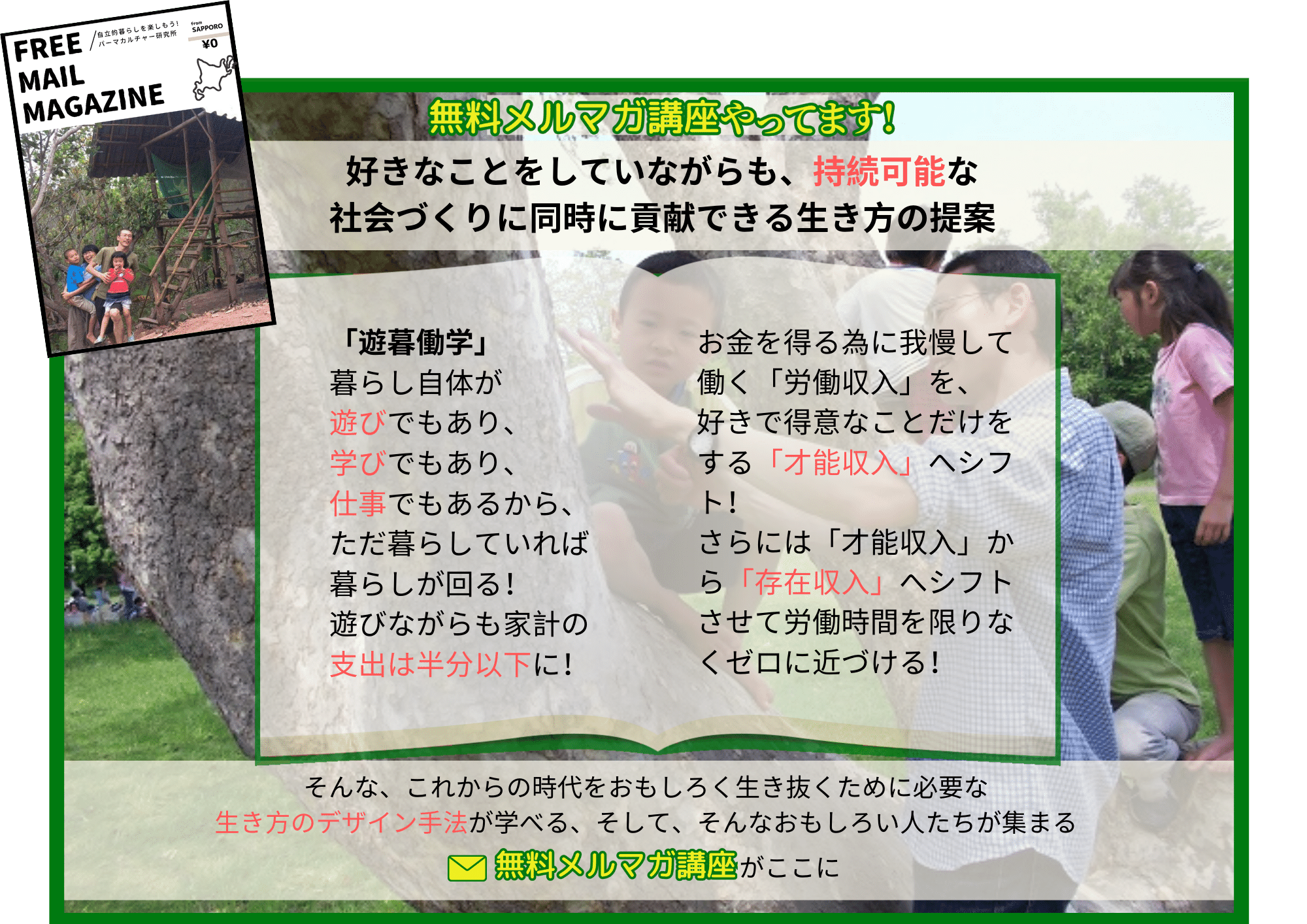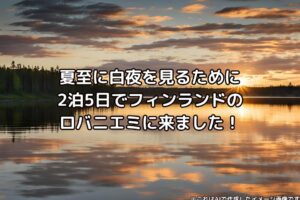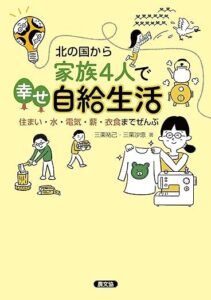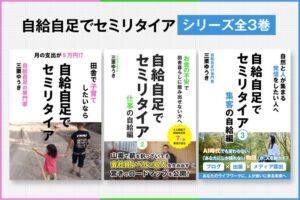2016年1月
パーマカルチャー研究所を立ち上げて5ヶ月が経過した時のこと。
タイのパーマカルチャー・ファーム「サハイナン」への長期滞在という、自主的「海外研修」。
サハイナン最終日

みんなと別れるのが寂しい気持ちもあった。
でも同時に、日本に帰るのがとても楽しみな気持ちもあった。
「日本に帰ったら、どんな暮らしをしようかな…」
ここでサンドットさんから学んだことはたくさんある。
一見、自然の中での暮らし方、を教えてもらったように見える。
でもぼくらが感じていたのは、それだけではなかった。
ぼくらが学んだのは、暮らしの楽しさ、おもしろさだった。
暮らすって、楽しい。
暮らしの中の困りごとを、自分たちの工夫や、みんなとの協力で一つずつ解決すること。
自分たちで作ったものを、みんなと一緒に喜び合ったり達成感を感じたり。
暮らしの中には、遊びの要素も、仕事の要素も、学びの要素もある。
暮らし=遊び=学び=働き、だ。
そんな風に考えて、「暮遊学働(ぼゆうがくどう)」という言葉を思いついた。
そうして、日本に帰って、通っていた、親子で通える「トモエ幼稚園」で、タイの暮らし報告会をさせてもらった。

園長にも、その時の暮らしを話して、「暮遊学働」という言葉を思いついたんですよ、と話すと、園長はこう言った。
「『遊暮働学(ゆうぼどうがく)』の方がいいんじゃないか?」
おぉ、確かに、なんかそっちの方が語呂がいいな。
なんかしっくりくる。
めっちゃいい言葉じゃん!
また、別の場所でもタイの報告会をやった。
その場所は、長沼のある方の自宅。
毎月、色々なテーマで自宅で勉強会を開催している方だ。
そこに、太陽光発電の講師として呼ばれたことをきっかけに、たびたび出入りするようになっていて、そこでも「遊暮働学」について話をした。
「この言葉、10年後には辞書に載ってますから」
調子に乗って、そんな風に豪語した。
(この時の「10年後」は、2026年。あと1年で辞書に載せなきゃ(^_^;)
暮らしの中で、できることがある
暮らしの中で、できることがある。
別にジャングルの中に住まなくても、室内に観葉植物を置くだけでもいい。
長ネギの根っこを切り落としたものを、ビンに入れた土にさせば、ネギがまた生えてくる。
大好きなビールを、自給する(自分で作る)こともできる。
サハイナンでやっていた冷蔵庫のない暮らし。
日本でだってできる。
そう思って、帰国直後に、それまでアパートで使っていた冷蔵庫も人にあげてしまった。

そうやって、サハイナンと同様、電気をあまり使わない暮らしをしていたら、4人家族のアパート暮らしなのに、電気代が600円を切ることもあった。
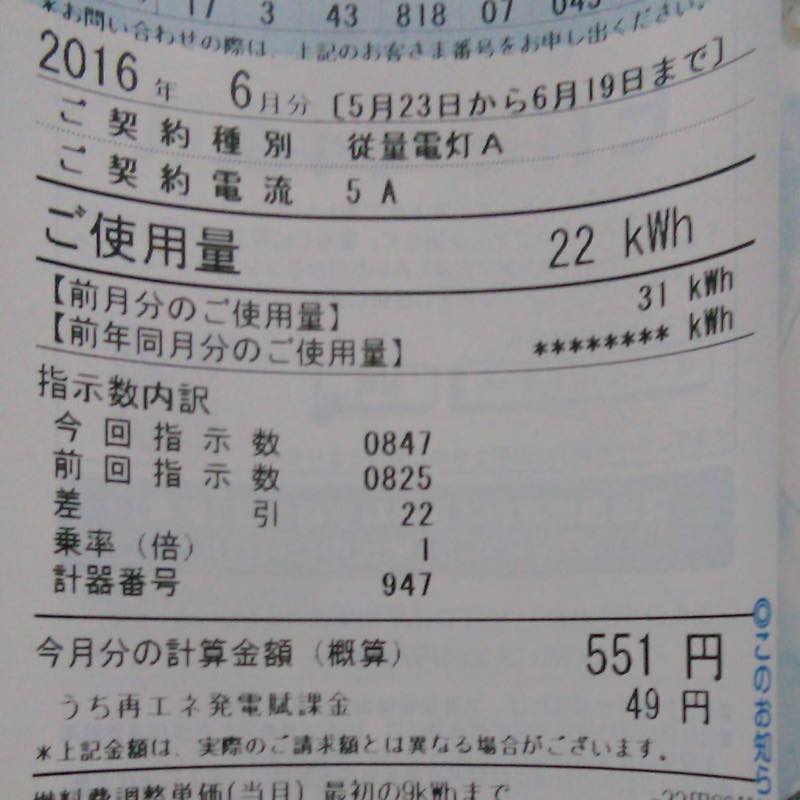
オフグリッド生活実験フィールドには、小屋を作り始めた。

コンポストトイレも作り、井戸掘りもやって、井戸水も得ることができた。

毎日がどんどん楽しくなった。
遊暮働学の実践。
暮らしが遊び。
楽しい。
でもそんな遊暮働学の日々も、時間が経つにつれて、現実的なお金の問題に直面する事になるのだけれど、それはまた別の機会にお話を…
以上、パーマカルチャー研究所を立ち上げて半年が経過した頃の話でした。
この時から、暮らし自体が、遊びで、学びで仕事である、だから究極、ただ暮らしていれば暮らしが回る、そんな「遊暮働学(ゆうぼどうがく)」のライフスタイルを実践しています。この暮らしの実現方法についての詳細を、無料のメルマガ講座でお伝えしていますので、興味のある方は、下のフォームからご登録ください。メールアドレスだけでも、登録できますよ。